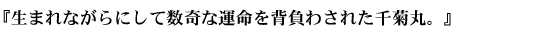
さてここからは、京の都での一休についてです。先ず、生い立ちはというと『年譜』は次のように
言ってます。(『年譜』のなかの「師」とあるのは一休のこと)
1394年(後小松皇帝 応永元年甲戌 )
『師は正統のちすじの人である。その母は藤氏で、南朝の高官の子孫であった。後小松天皇につかえ、
その側室となった。天皇は彼女を寵愛されたが、他の女官達が「彼女は南朝の義を守り、いつも剣を
しのばせて天皇をねらっている。」と讒言したので、皇后の奥殿を出て庶民の家に戸籍を入れ、師を
出産した。師は幼児の頃から貴人の相があったが、世間でこれを知っているものはいない。その出産は、
正月一日の日の出の時であった。』
一休のお母さんは伊予局(藤原氏・公家花山院某の娘)という方ですけど、館を追われはってからは、
都の奥里嵯峨の地蔵院という小さな庵に住まわれ、そこで帝の子を出産、生まれた子に「千菊丸」という
名をつけはりました。この乳飲み子千菊丸が、後の一休です。
生まれながらにして数奇な運命を背負われた千菊丸でしたけど、物心がつく頃になってお母さんから
生い立ちを聞かされても、そのことで寂しがったり、いじけたりすることもなく、お母さんの愛情を一身に
受けて明るく、活発で、知恵のある子へと育っていかれたといいます。けど、世の流れはそんな母と子を
いつまでも一緒に暮らさせておいてはくれんかったようです。この先いつ何時、北朝方の者が天皇の血筋の
わが子を狙うかも知れん、そんなことにでもなったら余りにもいたわしい、それならいっそのこと僧侶にして
命を守ろうと考えられたお母さんは、ある日千菊丸を呼んで「必ず立派なお坊さんになるのですよ」と、
涙ながらに諭してお寺へあずけられたのでした。
|
