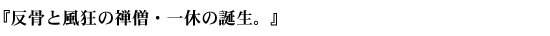
道号をさずかったことで、この後ますます過酷な修行に挑まれる一休でしたけど、あれは2年度の27歳の時でした。自分をさらに大きく変える出来事に出会われます。
その時のことを『年譜』は辻のように述べています。
1420年(応永廿七年庚子)師27歳。
『夏の夜、鴉の声を聞いて悟るところがあり、すぐにその見解を華叟和尚に示した。華叟は「それは羅漢(狭い範囲の悟り)の境涯であって作家の衲子(すぐれたはたらきのある禅者)にあらず」といわれた。そこで師は「私は羅漢で結構です。作家などにはなりたくない」といった。華叟は「お前こそ真の作家だ」といい投機の偈(悟りの詩)を作って呈出するようにいった。「凡とか聖とかの分別心や、怒りや傲慢のおこる以前のところを即今気がついた。そのような羅漢の私を鴉は笑っている。」』
私は今まで、父や母、有漏地や無漏地の様々を、ああだこうだと考え悩み、もだえ苦しんで27年も過ごして来たけど、今啼いて飛び去った鴉はそんな私の過去を一声で消してしまった。それだけではない、その啼き声の余韻に耳を澄ましていると、私の心のさらなる奥に何のまじりけもない心があることに気づいた。けど、和尚から、そんな考えは羅漢にすぎず作家の境地やないと言われると、私は羅漢で充分、作家などになりたくないなどと、いまだ自分の居場所にこだわるようなことを言ってしまった。なんと私は愚かで傲慢な人間なのだ。もともと、すぐれているとか普通とか、正しいとか悪いとか、こだわりとか執着とか、分別めいたそんなもんは一切ないのだ。羅漢も作家もないのだ。あるのは大自然の摂理だけだ、いまそれがよく分かった。だとすれば待てよ、さっき啼いたあの鴉は、単に啼いたのではなく、日常の心からいつまでたっても抜けだせずにいた、今までの私を笑たんだな、そうか、そうだったのか。
不幸せな母のもとに生まれた子が、純粋でありたいがために悩み苦しみ、師を求めて転々として、いま湖のはたの堅田でついに大悟された。
早速、華叟和尚は印可状をさずけようとしはるんですけど、一休は頑にそれを拒まれ、終いには破り捨ててしまわれたといいます。印可状を受け取られないのは謙翁和尚と同じで理解できますけど、破り捨ててしまうというのは普通やったら常軌を逸してることになると思います。けどその時の一休は、おそらく大悟をさらに徹底しようとされた、それと一休という禅僧のこれからの生き方をはっきりと示されたんやと思います。
まさにそれは、反骨と風狂の禅僧・一休の誕生を意味する出来事だったのです。
大悟して我が道を行くことに絶対の自信を得られた一休は、その後作家として独自の宗風をふりまかれ、堅田と京を行ったり来たり、時には病む華叟和尚のお伴をして法事などへも出かけられてたようです。
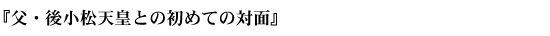
一休がお父さんの後小松天皇と初めて会われたのは34歳の時です。
『年譜』にはその時の様子が次のように書かれてます。
1427年(応永三十四年 丁末) 師34歳。
『後小松帝は神器を称光帝に授けられてから後は、御心を特に師に寄せられ、特に愛せられた。それで時々召され奉答せしめられたが、帝は席から乗り出して熱心に仏道を問い、禅の話をかわされ、大いに御心にかなった。』
34年目にして初めてお父さんと対面された一休は、この時どんな思いをもっておられたんやろう。場面としてはいろんな絵が浮かんできますけど、ひとつの考えに「その頃の一休はすでに分別を捨て去って高僧の域におられたはずや、そやから目の前にいる後小松帝をお父さんとも天皇とも思ておられんかったんと違うやろか。私は仏の道を説く人、目の前の人は仏の道を聞く人、つまり身分や立場をとっぱらった人間と人間との関係に過ぎんと思ておられたに違いない」というのがあります。その一方で「なんぼなんでも、肉親への恩まで捨て去ってはおられん。心の奥の奥では、きっとお父さんと呼ぼうとしておられたはずや、それとその場にお母さんも一緒やったらええのにな、と思われてたはずや」という考えもあります。どっちの考えも一休的やと思いますけど、『年譜』を見るがぎりでは、後者の考えが本心やと思わせる記述があります。
『師40歳、後小松帝が御病気になられた。崩御の数日前、勅して師を召された。師は密かに上皇の御書所に行き、直接お見舞いした。上皇の寝床のごく側で、法門の至極、宗門の奥義をお話したところ、喜びにお顔をほころばされた。そこで侍臣に命じ、箱を開かせ、先朝の立派な書籍や名人の草書、あるいは飛白などを数帖とり出して師に賜い、いわれた。「朕は昇天しても、これらの物や法の宝と共に居る。王位の陰の補佐は師の本職であって、朕がなにもいう事はない」。師は丁寧に拝をしてお別れをした。そしてついに10月20日崩御された。師は平常一本の針といえども蓄えるということをしなかった。余分なものはなおさらのことである。しかしこれらの書籍や硯などの宝は、小さなつづらに入れてどこへ行くにも持って歩き、片時も手離すことはなかった。』
宝物をさずけはった時の帝の本心は、もう余命いくばくもない、せめていま目の前にいるわが子の名を呼び抱きしめたい、ときっと思われてた。一休もまた、お父さんと呼びたかったはず。そうでなかったら宝物は受け取られなかった。ましてやお父さんからの形見の品とも思える宝物を死ぬまでそばに置いておくなんてことはされんかったと思います。ところで、お母さんの消息ですけど、一休の修行中にすでに亡くなっておられたとする書籍もありますけど、本当のところは分からないようです。年譜を書かれた墨斎さん(一休の弟子、没倫紹等)も人が悪い、ちょっと書いといてくれはったらよかったのに。立派になられた一休と会っておられたら、お母さんはどんなにうれしかったことやろ、と考えるとなんとも切なくなってきます。
|
